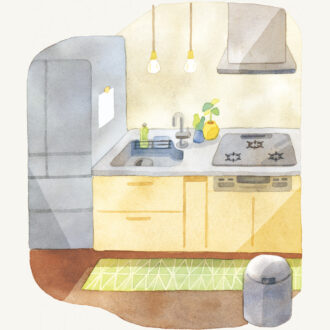【親の介護】
備えあれば憂いなし!
知っておけば安心の各種サービスを紹介
家族間のコミュニケーションが大切!
介護でストレスにならないために

介護は「マネジメント」
「親の介護というと、入浴やトイレ、食事の世話と思いがち。しかし、ケアを家族だけで担うのは大変ですし、プロに任せた方がうまくいく場合もあります。もっと広い意味で、家族にしかできない介護があります」(太田さん)。
例えば、通院に付き添って病状を聞く、介護サービスの内容をケアマネジャーと相談する。別居していても、親の様子を見に行ったり、電話することもあるでしょう。
また、親の経済状況を確認することも大切な役割です。
そう考えると、介護も一種のマネジメントと考えられます。離れていたり、仕事があってつきっきりの介護ができない人も、「親の世話を自分で見ないなんて……」と落ち込まずに、マネジメントも介護の形と考えれば、できることがあるはずです。
食事や排泄の介助なんて無理……と考える男性でも、いろんな人に連絡したり、介護の方針を決めるマネジメントなら、むしろ得意かもしれません。
家族間で「キーパーソン」を決める
親の介護にあたり、大切になるのがキーパーソンです。
親本人の意向を聞き、家族間の意見を調整する役割を担います。
例えば要介護者の家族が、ひとりは施設入所を希望し、別のひとりは在宅での介護がいいと言ったら、ケアマネジャーは誰の意見を聞いたらいいか戸惑います。
そんなとき、キーパーソンが本人に代わって窓口になって対応するのです。ほかにケアマネジャーと介護プランを決定したり、何かあった時の、緊急連絡先にもなります。
キーパーソンは必ずしも、親の近くにいる人がベストとは限りません。意見をまとめたり、交渉上手な人がいいので、男性にも向いています。
親が介護サービスの利用を拒否したら?
介護を子どもが抱え込まないためには、介護サービスを利用することが大切。
でも、当事者である親が「他人を家にいれたくない」「介護は家族がするもの」と考えていて、介護サービスを受けることをかたくなに拒否する場合があります。
「そんな時は、感情的になると、親子喧嘩で消耗するだけです。これもマネジメントのひとつとして客観的になって。取引先と接するときのように親の意見を聞きながら交渉しましょう」
説得法ですが、子どもの話は聞かない親でも第三者の意見には耳を傾ける傾向があります。
かかりつけの医師から介護保険の申請を勧めたらすんなり同意したというケースも多いそう。
ホームヘルプサービスに抵抗がある場合は、まず、訪問看護サービスの利用から提案すると、受け入れやすくなる場合もあります。
親を呼び寄せての介護は、うまくいく?
介護のために、遠方にいる親を呼び寄せたい人もいるでしょう。ただ、多くの親は住み慣れた家を離れたがりません。
義理の家族に気を使って窮屈な思いをしたり、家族が仕事に出ている間に一人きりになるのも心配です。
ご近所さんや友人もいる、住み慣れた環境にいて介護サービスを受けて暮らすほうがよい場合もあるので、よく相談を。
きょうだいで仲たがいひとりっ子の方がラク!?
法律上、親に対する扶養義務は、長男、長女の区別はなく、同居の子だけに世話をする義務があるわけではありません。でも現実は、誰かに負担が偏ったり、意見が対立することも。「ひとりっ子のほうが、介護の方針を決めやすくてラク、という意見もあるくらいです。それぞれの環境の違い、親への思いの温度差もあるので、話し合いで解決することが大切です。
子どもと親とどっちが大切?
出産年齢の高齢化が進み、子どもがまだ手のかかる年齢なのに、親の介護がスタートしてしまうという問題も増えています。
介護と育児どちらをとるか悩んだ場合は、介護はサービスなどを活用し、育児を優先することをおすすめしています。
病院は長居できない
医療保険の制度上、ケガや病気で入院する「急性期病院」は、通常、長期間入院することができません。
もっと長くリハビリを受けてから退院させたい場合は、医療ソーシャルワーカーに相談を。回復期リハビリテーション病院や、介護保険を利用できる老人保健施設などの、転院先探しを手伝ってくれます。
離れて暮らす親の健康チェック
親の多くは、子に心配をかけたくないため、具合が悪くても知らせないことが多いもの。親と話していて「あれ?」と思うことがあれば、メモをとって。
メモがたまって異変が感じられる場合は、地域包括支援センターに相談したり、受診の検討を勧めること。
また、保険証やお薬手帳の場所を共有してもらうなど、日ごろのコミュニケーションを大切にしましょう。
イラスト/丹下京子 文/田中絵真
大人のおしゃれ手帖2025年3月号より抜粋
※画像・文章の無断転載はご遠慮ください
関連記事
-
-
-
-
-
-
-
PR
-
PR
-
PR