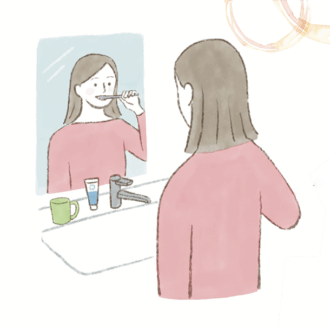更年期の不調をアロマでケア! おすすめの精油や楽しみ方を解説
更年期のセルフケアにおすすめの精油
更年期のセルフケアにおすすめの精油をご紹介します。精油は1種類だけ使ったり、複数のものをブレンドして使ったりする方法があります。

ラベンダー
アロマテラピーの代表的な精油であり、フローラルのやわらかい香りが人気です。鎮静作用があることから、ストレスの緩和やリラックス、快眠に役立ちます。
スイートオレンジ
フレッシュな甘いオレンジの香り。ストレスによるイライラや不安をやわらげたり、落ち込んだ気分を明るく前向きにしたりする作用があります。リラックス作用があり、快眠にも役立ちます。
ゼラニウム
ローズのような華やかな香りは特に女性に好まれています。女性ホルモンのエストロゲン様作用があり、気分の浮き沈みなどさまざまな更年期症状に効果があるといわれています。
クラリセージ
ハーブのさわやかな香りに加え、ナッツのような香りも持ち合わせています。女性ホルモンのエストロゲン様作用があり、さまざまな更年期症状に効果があるといわれています。
ペパーミント
精油成分にメントールを含み、フレッシュで清涼感のある香りです。リフレッシュ作用があり、眠気を抑えたり、ストレスをやわらげたりするのに役立ちます。また、鼻やのどの調子を整えるほか、虫よけ作用や消臭作用もあります。
ベルガモット
紅茶のアールグレイの香りづけに使用されており、柑橘のさわやかさとフローラルな甘さを併せ持つ香りです。リラックス作用があり、気分の浮き沈みを落ち着かせたり、ストレスによる不安や緊張をやわらげたりするのに役立ちます。
ティートゥリー
「ティーツリー」「ティートリー」とも呼ばれ、フレッシュで清潔感のあるすっきりした香りです。リフレッシュ作用があり、頭をすっきりさせたいときに役立ちます。また、免疫賦活作用、抗菌作用、抗ウイルス作用、抗炎症作用があります。
ネロリ
ビターオレンジの花の精油で、上品なフローラルの香り。リラックス作用があり、不安や緊張を鎮めて心を穏やかにしたいときや、睡眠の質を高めたいときに役立ちます。
この記事のキーワード
この記事を書いた人
ファッション、美容、更年期対策など、50代女性の暮らしを豊かにする記事を毎日更新中!
※記事の画像・文章の無断転載はご遠慮ください
Instagram:@osharetecho
Website:https://osharetecho.com/
お問い合わせ:osharetechoofficial@takarajimasha.co.jp
関連記事
-
-
-
-
-
-
-
PR
-
PR
-
PR