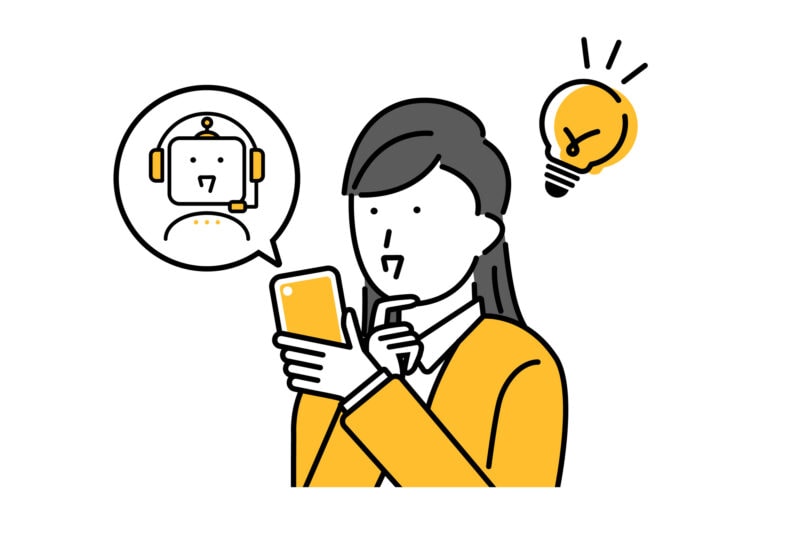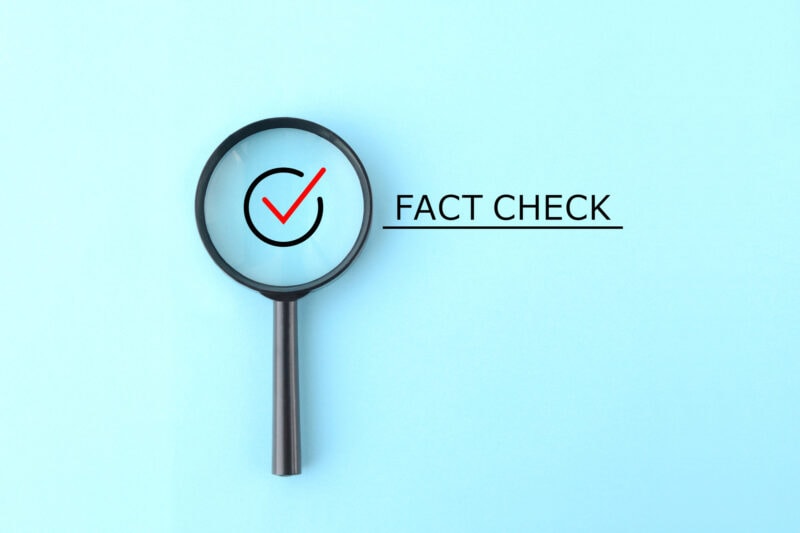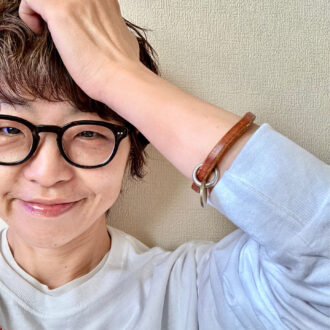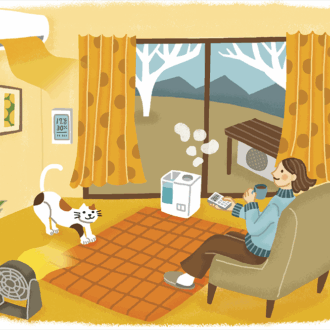【AIのある暮らし】有能なパートナー!日進月歩のAI技術で、毎日の生活や働き方をもっと豊かに、快適に
久武ミキ

AI(Artificial Intelligence<アーティフィシャル・インテリジェンス>)とは、コンピュータが人間のように学習と推論を繰り返し、自ら意思決定を行う技術やシステムのこと。身近なところでは、音声アシスト機能やロボット掃除機などにAIが活用されていることはご存じの方も多いでしょう。すでに私たちの暮らしに溶け込み、知らず知らずのうちに活用しているAIですが、具体的にどんなことができるのか、暮らしにどんな変化をもたらすのかということまでは踏み込めていない人も多いのではないでしょうか。日夜目覚ましい進化を遂げるAI技術を知ることは、私たちの未来の暮らしを俯瞰すること。そこで、教育などを中心にICT機器の効果的活用について研究する摂南大学の小林正樹教授に、AIの魅力やその活用法についてお話を伺いました。
私たちの暮らしにAIは必要?
 すでに私たちの気づかないところでAIは幅広く活用され、これまで人間が行ってきた作業の時間短縮や効率化が行われています。たとえば、私たちが検索エンジンを使用すると、これまでは多くの候補が表示され、それらを一つずつチェックし、正しい情報を精査するという手順でしたが、近年では検索結果の前に「AIによる概要」というものが表示されるようになりました。ここでは間違った情報は除外され、複数サイトから得られた正しい情報だけがまとめられています。これにより、私たちは素早く、正確な情報を得ることが可能になりました。また、文字や音声で人間と会話をするように自動で回答を出してくれる便利な「チャットボット」なども活用している人は多いはず。毎日の生活のなかでSiriやアレクサなどの音声アシスタントで、その快適さや有用性を感じている方も多いのではないでしょうか。
すでに私たちの気づかないところでAIは幅広く活用され、これまで人間が行ってきた作業の時間短縮や効率化が行われています。たとえば、私たちが検索エンジンを使用すると、これまでは多くの候補が表示され、それらを一つずつチェックし、正しい情報を精査するという手順でしたが、近年では検索結果の前に「AIによる概要」というものが表示されるようになりました。ここでは間違った情報は除外され、複数サイトから得られた正しい情報だけがまとめられています。これにより、私たちは素早く、正確な情報を得ることが可能になりました。また、文字や音声で人間と会話をするように自動で回答を出してくれる便利な「チャットボット」なども活用している人は多いはず。毎日の生活のなかでSiriやアレクサなどの音声アシスタントで、その快適さや有用性を感じている方も多いのではないでしょうか。
AI ってなんだか難しそう……その壁、どうやって乗り越える?
 「未知のもの=恐ろしい」そんなふうに感じている方はきっと多いと思います。昔、世界に初めて「電気」が登場したときも、最初は「恐ろしいもの」として普及が進まなかったともいわれています。機械は「それを使っている」という実感がないことが一番よい状態。乗用車を運転するのに、エンジンやモーターの仕組み、空気抵抗など難しいことを知らなくても運転できるのと同じです。私たちはAIの「深層学習」や「ニューラルネットワーク」といった根本的な考え方や技術を知らなくても、ただ便利にAIを利用すればよいだけ。スマートスピーカーに「電気をつけて」とお願いしたことがある人は多いと思いますが、これからはAI導入によって「暗くなってきたら自動的に電気をつけて」というような一歩進んだ注文ができるようになります。AIを「使ってみよう!」と意気込まなくていい。それこそがAIが生活のなかに溶け込んでいる証です。
「未知のもの=恐ろしい」そんなふうに感じている方はきっと多いと思います。昔、世界に初めて「電気」が登場したときも、最初は「恐ろしいもの」として普及が進まなかったともいわれています。機械は「それを使っている」という実感がないことが一番よい状態。乗用車を運転するのに、エンジンやモーターの仕組み、空気抵抗など難しいことを知らなくても運転できるのと同じです。私たちはAIの「深層学習」や「ニューラルネットワーク」といった根本的な考え方や技術を知らなくても、ただ便利にAIを利用すればよいだけ。スマートスピーカーに「電気をつけて」とお願いしたことがある人は多いと思いますが、これからはAI導入によって「暗くなってきたら自動的に電気をつけて」というような一歩進んだ注文ができるようになります。AIを「使ってみよう!」と意気込まなくていい。それこそがAIが生活のなかに溶け込んでいる証です。
AI活用することのメリットとは?
 コンピュータは「繰り返し」が得意。この「繰り返し」の作業を「高速」で行えるのがAIです。そうしたメリットに加え、人間の“考え方”に似せた頭脳の構造を採用し、ここ数年でAIは爆発的な発展を遂げました。試しに「今晩のおかずは何にしよう?」とAIに問いかけてみてください。その際に「今日はとても暑い日だ。家からスーパーマーケットが遠い。アレルギーで○○は食べることができない。昨日はカレーで一昨日はハンバーグだった」といった、さらに詳しい情報をAIに教えてあげてください。場合によってはデータベースとしてファイルでAIに提供してあげてください。きっとAIは、ベストなアイデアを提供してくれると思います。その他にも敬語を含んだ文章の校正や冠婚葬祭時のマナーなど、あなたの「困った」にAIは答えてくれます。
コンピュータは「繰り返し」が得意。この「繰り返し」の作業を「高速」で行えるのがAIです。そうしたメリットに加え、人間の“考え方”に似せた頭脳の構造を採用し、ここ数年でAIは爆発的な発展を遂げました。試しに「今晩のおかずは何にしよう?」とAIに問いかけてみてください。その際に「今日はとても暑い日だ。家からスーパーマーケットが遠い。アレルギーで○○は食べることができない。昨日はカレーで一昨日はハンバーグだった」といった、さらに詳しい情報をAIに教えてあげてください。場合によってはデータベースとしてファイルでAIに提供してあげてください。きっとAIは、ベストなアイデアを提供してくれると思います。その他にも敬語を含んだ文章の校正や冠婚葬祭時のマナーなど、あなたの「困った」にAIは答えてくれます。
AIを利用する上で気をつけること
 ネット検索した情報の真偽は常につきまとうもの。しかし、これはAIによってずいぶん改善されてきていると思います。AIの情報源も基本ネットではありますが、現代のAIは複数のサイトを検索し、それらを総合的に判断して結論を出しています。たとえば新聞記事でも、総務省発表の何らかのデータを元に記事が書かれている場合には、その元データが「一次情報」、新聞記事が「二次情報」、さらにその新聞記事を元に書かれたコラムなどが「三次情報」と呼ばれ、加工されるたびに本来のデータから遠ざかって、誤情報へと変化していくことがありますが、AIはその「一次情報」までさかのぼることが多いため、近年では間違った情報が少なくなってきているのです。とはいえ、AIにもまだ弱点はあります。それは情報の速達性。AIはウェブ上のさまざまな情報をベースとしているため、最新情報には疎いことが多い。有料版を利用することで多少は解消されますが、それでも古いと感じることがあります。AIの進化は恐ろしいほどのスピードで進んでいます。この記事を執筆した時点の状況も、皆さんが読んでいる頃にはすでに古い情報になっているかもしれません。「AIもまだ万能ではない」と理解した上で利用するのが賢い活用法ではないでしょうか。
ネット検索した情報の真偽は常につきまとうもの。しかし、これはAIによってずいぶん改善されてきていると思います。AIの情報源も基本ネットではありますが、現代のAIは複数のサイトを検索し、それらを総合的に判断して結論を出しています。たとえば新聞記事でも、総務省発表の何らかのデータを元に記事が書かれている場合には、その元データが「一次情報」、新聞記事が「二次情報」、さらにその新聞記事を元に書かれたコラムなどが「三次情報」と呼ばれ、加工されるたびに本来のデータから遠ざかって、誤情報へと変化していくことがありますが、AIはその「一次情報」までさかのぼることが多いため、近年では間違った情報が少なくなってきているのです。とはいえ、AIにもまだ弱点はあります。それは情報の速達性。AIはウェブ上のさまざまな情報をベースとしているため、最新情報には疎いことが多い。有料版を利用することで多少は解消されますが、それでも古いと感じることがあります。AIの進化は恐ろしいほどのスピードで進んでいます。この記事を執筆した時点の状況も、皆さんが読んでいる頃にはすでに古い情報になっているかもしれません。「AIもまだ万能ではない」と理解した上で利用するのが賢い活用法ではないでしょうか。
AI活用で起こり得るリスクとは?
 ニュースなどでも取り上げられているように、学生たちが提出するレポートが「大量生産」になっていることは由々しき問題です。実際に私が課題提出を求めた際のレポートでも、半分以上が同じアイデアだったという残念な出来事がありました。そのため今の教育現場では「AIといかに付き合うべきか」その方法が検討されています。これは学生だけに限ったことではありません。大人も、会社での提出物にAIを活用する人は増えています。人間は「考える葦」。自ら発想する力を手放してしまったら、人は人ではなくなります。同様に、ネット上の意見やインフルエンサーの訴え、怪しげなウェブ広告に惑わされて、自分の確固たる「ものの考え方」が揺らいでしまい、一時の潮流に流されてしまうケースも増えています。思考は人間に備わっている偉大な力です。私たち人間がAIを利用する際は、その便利さにかまけたり、鵜呑みにしてしまったりしないように注意しなければならないと思います。
ニュースなどでも取り上げられているように、学生たちが提出するレポートが「大量生産」になっていることは由々しき問題です。実際に私が課題提出を求めた際のレポートでも、半分以上が同じアイデアだったという残念な出来事がありました。そのため今の教育現場では「AIといかに付き合うべきか」その方法が検討されています。これは学生だけに限ったことではありません。大人も、会社での提出物にAIを活用する人は増えています。人間は「考える葦」。自ら発想する力を手放してしまったら、人は人ではなくなります。同様に、ネット上の意見やインフルエンサーの訴え、怪しげなウェブ広告に惑わされて、自分の確固たる「ものの考え方」が揺らいでしまい、一時の潮流に流されてしまうケースも増えています。思考は人間に備わっている偉大な力です。私たち人間がAIを利用する際は、その便利さにかまけたり、鵜呑みにしてしまったりしないように注意しなければならないと思います。
家庭や職場でAIを活用できる場面って?
 冷蔵庫のなかにある食材をすべて入力してみてください。それらの食材から「何が作れるか」をAIに問いかけてみると、人間が想像するよりもはるかに多くのメニューを提案してくれます。買い物では、冷蔵庫の中身が入力されているだけで「在庫の有無」、作りたい料理に「足りない材料」も提案してくれます。健康管理では、たとえば毎日の歩数をAIに読み込ませておけば「月曜日は歩数が少ない」「前年、同時期と比較して歩数がこれだけ多い」といった分析を自動で行い、健康管理についてのアドバイスをしてくれます。仕事では、プレゼンテーションソフトに特化したAIがあり、プログラミングならおおよその部分はAIが書いてくれたり、得られたデータの分析も自動的に行ってくれたりします。その他にも画像・動画・音声の生成・加工機能など、活用方法や楽しみ方、付き合い方は人それぞれ。AIは、人間にとってまさに「有能な相棒」なのです。
冷蔵庫のなかにある食材をすべて入力してみてください。それらの食材から「何が作れるか」をAIに問いかけてみると、人間が想像するよりもはるかに多くのメニューを提案してくれます。買い物では、冷蔵庫の中身が入力されているだけで「在庫の有無」、作りたい料理に「足りない材料」も提案してくれます。健康管理では、たとえば毎日の歩数をAIに読み込ませておけば「月曜日は歩数が少ない」「前年、同時期と比較して歩数がこれだけ多い」といった分析を自動で行い、健康管理についてのアドバイスをしてくれます。仕事では、プレゼンテーションソフトに特化したAIがあり、プログラミングならおおよその部分はAIが書いてくれたり、得られたデータの分析も自動的に行ってくれたりします。その他にも画像・動画・音声の生成・加工機能など、活用方法や楽しみ方、付き合い方は人それぞれ。AIは、人間にとってまさに「有能な相棒」なのです。
実際に、AIに「気になること」を聞いてみよう!
 まずは「ChatGPT」「Copilot」「Gemini」などを開き、「女性の健康に役立つツールを教えて」など、気になる質問を投げかけてみてください。AIは即座に見合った答えをまとめ、項目に分けて、読みやすい文章にして返してくれることでしょう。さらにAIに繰り返し質問していくことで、質問者側も「いかに尋ねれば求めていた答えを引き出せるか」そのコツがつかめてくるはずです。AIが進化するように、人間もAIを利活用する側として成長する必要があります。悪意のある情報に惑わされず、フェイクを見抜く力を養い、正しい情報を取捨選択する。やがてAIも、人だけが持っていた「見抜く力」を装備する時代がくるかもしれませんが、今はまだ、正しい答えを導き出すためには「人間力」が必要なのです。
まずは「ChatGPT」「Copilot」「Gemini」などを開き、「女性の健康に役立つツールを教えて」など、気になる質問を投げかけてみてください。AIは即座に見合った答えをまとめ、項目に分けて、読みやすい文章にして返してくれることでしょう。さらにAIに繰り返し質問していくことで、質問者側も「いかに尋ねれば求めていた答えを引き出せるか」そのコツがつかめてくるはずです。AIが進化するように、人間もAIを利活用する側として成長する必要があります。悪意のある情報に惑わされず、フェイクを見抜く力を養い、正しい情報を取捨選択する。やがてAIも、人だけが持っていた「見抜く力」を装備する時代がくるかもしれませんが、今はまだ、正しい答えを導き出すためには「人間力」が必要なのです。
AIの活用術についてお話を伺ったのは…
摂南大学 経営学部 経営学科
小林 正樹 教授(専門:教育工学)
高等教育における大人数教育を専門とし、大学教育にICT機器を効果的に活用する手法を研究。授業中に学生一人ひとりに情報が行き渡る双方向システムの開発に取り組んでおり、AIやVR導入の新たな授業形態、特に令和時代の教室レイアウトを模索している。著書には『ビジネスデータの分析リテラシーと活用』(共著)等がある。