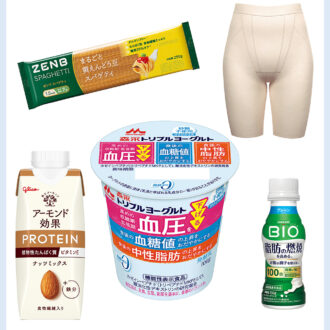「しあわせは食べて寝て待て」でも話題! “薬膳”で梅雨の体調不良対策を

ドラマ「しあわせは食べて寝て待て」でも注目されている「薬膳」を手軽に取り入れてみませんか。梅雨は湿気や気温差、低気圧などの影響で体調不良が起こりやすい時期。そんな時こそ薬膳で調子を整えましょう。
ドラマで話題の薬膳とは
ドラマ「しあわせは食べて寝て待て」は水凪トリさんの同名漫画が原作。桜井ユキさん演じる主人公の麦巻さとこさんが一生付き合わなくてはならない病気(膠原病)を発症し、「薬膳」と団地の人々との交流によって生きる気力を取り戻していく物語です。
主人公・さとこさんが出会った薬膳の魅力
さとこさんが出会った「薬膳」とは、漢方の理論をもとに体調や体質、症状、季節に合わせてとる食事のこと。
漢方の思想である「医食同源」とは、「食べるものと薬になるものの源は同じ」という意味です。たとえば生姜は「ショウキョウ」、しそは「蘇葉(ソヨウ)」など、私たちが普段食べている食材は漢方の原料としても使われています。
また、東洋医学では、旬の食材は体を整える作用があると考えます。旬の食材を中心に、自分の体調や体質に合わせた食材を選ぶことで体の調子を整えていくのが薬膳です。
梅雨の「未病」対策にも薬膳
梅雨は湿度が高く水分代謝が低下しやすいほか、低気圧や寒暖差の影響で自律神経が乱れやすいことから体調不良が起こりやすい時期です。
梅雨の時期に「体がだるい」「食欲がわかない」「体が冷える」などと感じる人がいますが、こうした「病気ではないが健康でもない状態」を「未病」といいます。東洋医学では、未病の対策は薬だけでなく食事も重要とされています。
たとえば、5~7月に旬を迎える「うめ」は水分代謝を整える作用があり、湿度が高い梅雨や夏にぴったりの食べ物です。
知っておきたい用語「気・血・水(き・けつ・すい)」
薬膳を取り入れるうえで知っておきたい用語のひとつが「気・血・水(き・けつ・すい)」です。東洋医学では、人間の体は「気・血・水」という3つの要素で構成されると考えます。「気」は生命エネルギー、「血」は血液とその働き、「水」は体内の血液以外の体液のこと。
「気・血・水」がうまく巡ることで健康が保たれ、これらが不足したり、滞ったりすることでバランスが崩れると不調が出ると考えられています。
なお、薬膳は病気を予防するための食事であり、万能薬ではありません。そのことを理解したうえで、自分の状態に合う食事を取り入れて元気な体づくりに役立てましょう。
この記事を書いた人
作りおき料理コーディネーター・薬膳マイスターかみはらえりこ
「女性が生きやすい社会づくりへの貢献」をモットーに、食や健康、美容など女性が笑顔になれる情報を発信中。